
2025年06月22日(日)
植村友香さん(遺愛女子高等学校_2年生)
コンクリートは私たちの生活空間や社会基盤の構築に必要不可欠な建材です。CO2削減が重要視される近年、ジオポリマーという低炭素コンクリートの研究開発、実用化が進められています。
今回はジオポリマーの一種であるEeTAFCONの研究開発を行うEeTAFCON研究会様に取材をさせていただき、従来のコンクリートとの比較や期待される効果、普及の現状と今後の展望について伺いました。
EeTAFCONとは
従来のコンクリートとは異なり、EeTAFCONはセメントを使用せずに代替としてFA(フライアッシュ)や高炉スラグ微粉末を使用します。ここで水ではなくアルカリ水を使用するのは、FAが高pHまたは低pHによく溶けて反応しやすく、酸性溶液よりも強度をだすのが容易で扱いやすいためです。
.jpg)
資料提供:EeTAFCON研究会 様
FA(フライアッシュ)の有効活用
FAは石炭火力発電の副産物である石炭灰の約9割を占めています。石炭灰は年間で6割(800万トン)以上がセメント原材料として有効利用されているため、今後予想されるセメント生産量の減少に対応するための新しい有効利用技術が求められます。
そこで、セメントの代わりにFAを利用するEeTAFCONはまさにこの需要に適しているのです。
CO2削減に大きく貢献
.jpg)
セメントは製造工程で多量のをCO2排出します。
1トンのセメントを生産するには、粉砕した石灰石(炭酸カルシウム)や石炭灰などを焼成する際の熱分解によって約480kg、さらにこれを粉砕するための化石エネルギーまたは電力消費によって約280kg、合計約760kgのCO2を排出します。
もし粉砕する際に再生可能エネルギーを利用したとしても熱分解による約480kgのCO2排出を削減することは難しいのです。
EeTAFCONはこの熱分解を起こす焼成反応を回避することでCO2削減を実現しており、工程全体を通してはセメントコンクリートと比べ約70%もの排出量削減が可能になります。
.jpg)
資料提供:EeTAFCON研究会様
優れた耐久性
①耐酸性全国各地で問題となっている下水道管の老朽化は、下水から発生した硫化水素が管の上部内面に吸着し、酸化によって硫酸を生じてコンクリートを腐食することで進行します。
硫酸水溶液への浸漬試験の結果では、従来コンクリートの質量は大きく減少しているのに対して、EeTAFCONは変化していません。
このような高い耐酸性により下水道、温泉地など酸劣環境の設備の長寿命化が期待されます。
.jpg)
資料提供:EeTAFCON研究会 様
②耐塩害性
もう一つの大きな利点は遮塩性が極めて高いことです。
塩水浸漬試験の結果では同じ経過年数の他のコンクリートと比べると、塩化物イオンの浸透が大幅に抑えられています。
遮塩性を活かし、橋の部材としての実用化も進められています。
.jpg)
塩水浸漬試験(土木学会基準 JSCE-G572)
資料提供 EeTAFCON研究会 様
普及の現状と課題
現在、日本でのジオポリマーの利用は土木が中心です。建築物への利用は性能的には可能なものの、特に地震が多い日本では建築物に用いるコンクリートの仕様などについて厳しい規制があり、社会実装が困難でした。
しかし、2025年4月にセメント不使用コンクリートも大臣認定を取得することで建築物へ利用できるようになったため、今後は建築物へのジオポリマーの利用に向けた活動が期待されます。
EeTAFCONも主に土木用途で使用されており、施工例としては、既述の橋用部材の他にもマンホール、側溝、歩車道境界ブロックなどがあります。
今後の用途展開の可能性としては、ポールや建材パネルが検討されています。
課題としては、アルカリ水が高価なため製造コストが高いこと、製造するための知識と技術の普及が挙げられますが、EeTAFCON研究会様は市場拡大、信頼性の確保、技術の普及の3点に基づいて社会実装の加速をを目指しています。
おわりに
今回の取材を通し、多量のCO2を排出するセメント産業がカーボンニュートラルに資するためどのような研究開発、実用化に向けた活動を行っているのかを学ぶことができました。時代のニーズに応えるためには、建設や環境といった異なる分野の知見を結集し、社会問題の解決に繋げる発想が重要だと感じました。
EeTAFCONは、副産物を有効利用し大幅なCO2削減を実現するという点でSDGsに適っているだけではなく、高い耐久性も兼ね備えていることから、インフラ建設においてより使用されるべきです。
最後に、取材にご協力いただいた皆様、本当にありがとうございました。
今回の貴重な経験を通して、今後も持続可能な技術の進展に注目していきたいと思います。
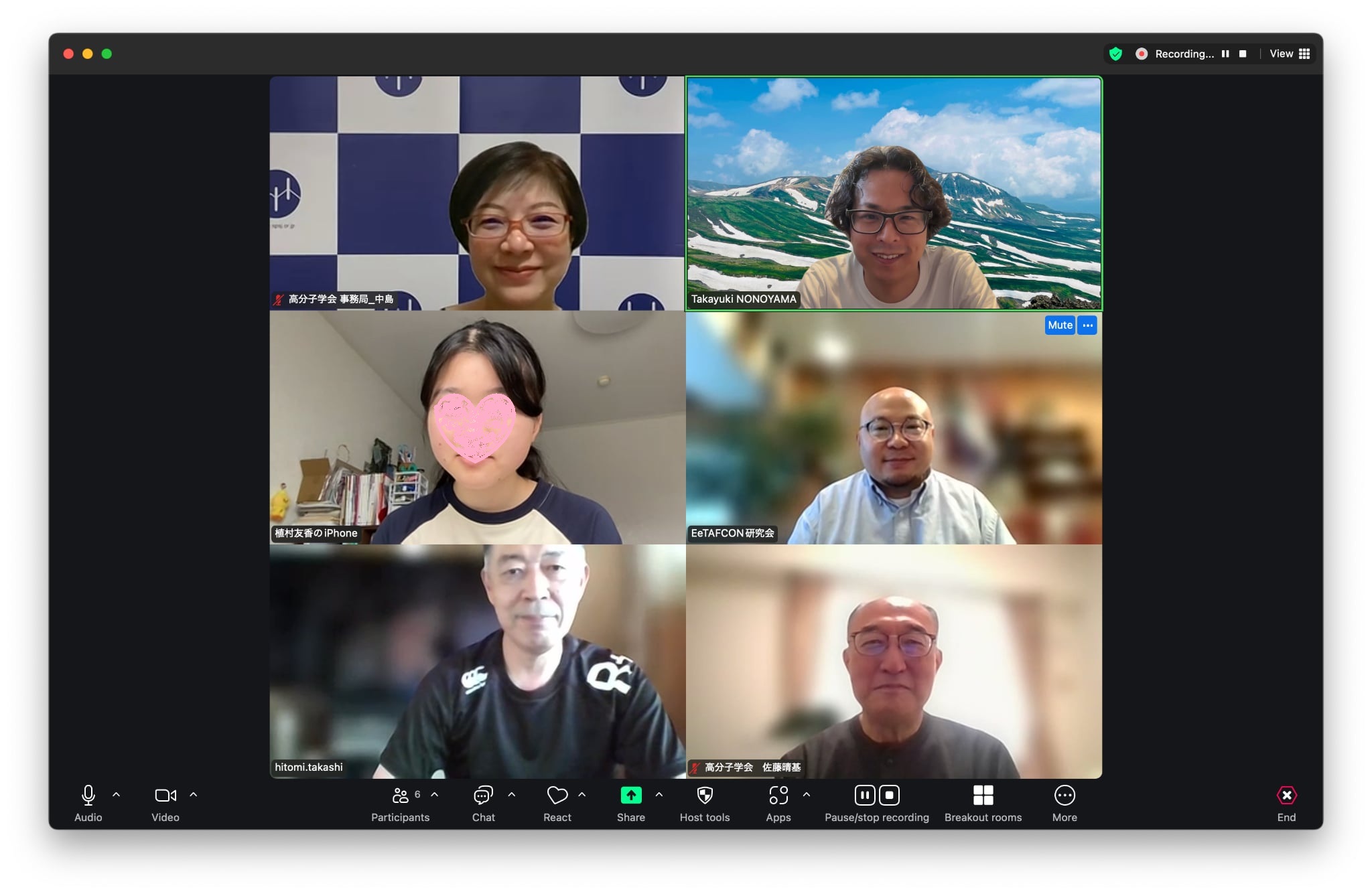
取材先:EeTAFCON研究会
取材日:2025年6月22日(日)
取材日:2025年6月22日(日)


